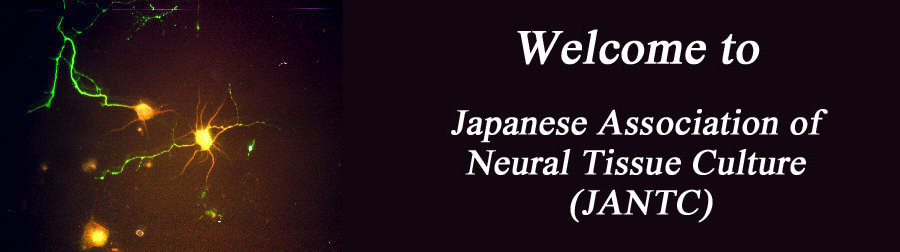
Back number
世話人名簿
第1回(平成6年8月27日)
東京慈恵会医科大学高木会館7階GHK会議室
A.Talk:
1.シュワン細胞と神経栄養因子:渡部和彦(東京慈恵会医科大学神経病理)
2.オリゴデンドロサイトの分化と中枢ミエリンの形成機構:阿相晧晃(慶応義塾大学医学部 生理学)
3.3次元培養法の神経再生研究への適用:堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生理学)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson
特別講演(平成6年9月27日)東京慈恵会医科大学高木会館7階K会議室
ヒト・オリゴデンドロサイトの生物学:Seung
U. Kim (Division of Neurology, Univ. of
British
Columbia)
第2回(平成7年3月4日)
東京慈恵会医科大学本館講堂
A.Talk:
1.5-FU誘導体の神経毒性の機序に関する組織培養による研究:秋葉智英(興和
(株) 富士
研究所)
2.脾抗体分泌細胞に対する知覚神経の効果:樋川直司(横浜市立大学医学部第1生理学)
3.培養神経細胞を用いた運動ニューロン疾患へのアプローチ:道川 誠(東京医科歯科大学
神経内科)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson(その2)
C.Do-It-Yourself
Journal Club
1.渡部和彦(東京慈恵会医科大学神経病理)
2.堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生理学)
3.松本 陽(東京都神経科学総合研究所神経病理)
第3回(平成7年8月26日)
東京医科歯科大学・医科新棟5階症例検討室
A.Talk:
1.合成ペプチド抗体の作成と応用:水口 雅(国立精神・神経センター神経研究所疾病2)
2.神経細胞に
iNOS
は存在するか:佐藤郁子(東京医科歯科大学細胞機能制御講座)
3.Competitive
PCR
による脳内サイトカインの定量的解析:田沼直之(東京都神経科学総
合研究所神経病理)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson(その3)
C.Do-It-Yourself
Journal Club
1.渡部和彦(東京慈恵会医科大学神経病理)
2.松本 陽(東京都神経科学総合研究所神経病理)
3.竹島多賀夫(鳥取大学医学部神経内科)
第4回(平成8年3月16日)
東京慈恵会医科大学高木会館7階GHK会議室
A.Talk:
1.臓器型神経組織培養法の技術的変遷;Maximow
2枚カバースリップ法からデイスポー
ザブル容器法まで:石原好弘(東京都神経科学総合研究所神経病理),田島たよ子(東京
医科歯科大学難治疾患研究所神経病理)
#
Product information; HB-GAM (10 min): Brigitta Tadmor (Becton Dickinson, USA)
2.脳および末梢神経内膜微小血管由来内皮細胞を用いた血液脳関門・血液神経関門のin
vitro
モデル作製の試み:神田 隆(東京医科歯科大学神経内科)
3.リンパ組織の交感神経支配誘導メカニズム
ー 共生培養法による検討 ー:河南有希子(大
阪府立大学農学部獣医生理学
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson(その4)
C.Current
progress
1.Competitive
RT-PCR:渡部和彦(東京慈恵会医科大学神経病理)
2.EAEとNK細胞:松本 陽(東京都神経科学総合研究所神経病理)
3.PASII
/ PMP22:武田泰生(慶応義塾大学医学部生理学)
第5回(平成8年8月31日)
東京医科歯科大学・医科新棟5階症例検討室
A.Talk:
1.細胞接着分子L1の構造と機能:武田泰生(慶応義塾大学医学部生理学)
2.Microexplant
culture
を用いたマウス小脳顆粒細胞の移動挙動:永田 功(東京都神経
科学総合研究所神経細胞生物学)
3.成熟哺乳動物の網膜培養と神経突起再生:高野雅彦(横浜市立大学医学部眼科)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson
その5
C.Current
progress
1.肝由来神経活性化因子による末梢神経再生促進:堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生理
学)
2.IMR32細胞の形態変化と蛋白質動態:石岡憲昭(東京慈恵会医科大学DNA医学研究所)
3.結節性硬化症遺伝子産物の脳内発現:水口 雅(自治医科大学小児科)
第6回(平成9年3月22日)
場所:慶應義塾大学医学部・新教育研究棟4階講堂
A.Talk:
1.グリア系細胞系譜における
Substance P の関与:野津智美(慶応義塾大学医学部生理学)
2.リソゾーム蓄積症の遺伝子治療:大橋十也(東京慈恵会医科大学小児科)
3.アストロサイトの分化におけるGFAP遺伝子の発現調節機構:馬場広子(国立生理学研
究所神経情報部門)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson
その6
C.Current
progress
1.外傷部位におけるO-2A
progenitor cellからtype-2 astrocyteへの分化誘導について:
村上健一(慶応義塾大学医学部生理学)
2.マウス培養神経細胞株Neuro2aを用いたプレセニリン1遺伝子変異によるアルツハイマ
ー病発症機構の解析:駒野宏人(国立長寿医療研究センター痴呆疾患研究部)
3.アデノウイルス・ベクターを用いたグリア細胞株由来神経栄養因子
(GDNF)の遺伝子導
入:渡部和彦(東京都神経科学総合研究所神経病理部門)
第7回(平成9年8月30日)
場所:東京医科歯科大学・医科新棟5階症例検討室
A.Talk(各30分):
1.GM2ガングリオシドーシス:ヒトとモデルマウスとの相違:Functional
redundancy in the
β-hexosaminidase
enzyme system:三五一憲(国立健康栄養研究所老人健康栄養部)
2.変態における両生類幼生の尾の退縮の分子機構:矢尾板芳郎(東京都神経科学総合研究所
分子神経生物学部門)
3.神経接着分子とコンドロイチン硫酸プロテオグリカンの機能相関:in
vivoとin vitro:
川野 仁(慶應義塾大学医学部解剖学),武内恒成(国立奈良先端科学技術大学院大学バ
イオサイエンス研究科)
B.Do-It-Yourself
Journal Club(各15分)
1.EAEにおけるサイトカインの役割:competitive
PCRによる解析:田沼直之(東京都神
経科学総合研究所神経病理部門)
2.Microisland
cultureを用いたドパミン神経栄養因子のアッセイ:竹島多賀夫(鳥取大学
医学部脳神経内科)
3.神経再生におけるIL-1β,
IGF-I , IGF-IIの役割:堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生
理)
第8回(平成10年3月28日)
場所:東京都老人総合研究所・4階大会議室
A.Talk:
1.神経系構築過程におけるマウスカドヘリン6の役割:井上高良(国立精神神経センター神
経研究所疾病研究第7部)
2.オリゴデンドロサイトの発生と分化を調節するアストロサイト:阿相晧晃(東京都老人総
合研究所細胞生物学部門)
3.培養下における神経筋接合部の形成と筋特異的蛋白の発現,制御機構:小林高義(東京医
科歯科大学神経内科)
B.Exhibition:日本Becton-Dickinson
その7
C.Current
progress:
1.Mini-review:
神経発達におけるNCAMの糖鎖PSAの機能:石 龍徳(順天堂大学医学
部第2解剖)
2.新しい神経特異的アクチン調節蛋白質
Clipin C:武内恒成(国立奈良先端科学技術大学
院大学バイオサイエンス研究科)
第9回(平成10年8月29日)
場所:東京医科歯科大学・医科新棟5階症例検討室
A.Session
I
1.細胞膜裏打ちアクチン結合蛋白質ClipinとERM分子群の機能:武内恒成(国立奈良先端
科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)
2.神経-免疫ネットワーク:リンパ球由来カテコールアミンと交感神経成長因子としてのサ
イトカインの役割:河南有希子(大阪府立大学農学部獣医生理学講座)
3.癌抑制遺伝子p16
(INK4a)
発現による腫瘍細胞の形質変化:膠芽腫細胞での検討:佐和
弘基(杏林大学医学部脳神経外科)
4.3Dマトリックス中でのニューロンの移動と分化:永田 功,木村-黒田純子(東京都神
経科学総合研究所神経細胞生物学部門),阿相晧晃(東京都老人総合研究所神経生物学部
門)
B.Exhibition:ナルジェ・ヌンク・インターナショナル(株)
C.Session
II
5.成熟動物中枢神経再生in
vitroモデル:堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生理),高野
雅彦(横浜市立大学医学部眼科)
6.ラット脊髄神経節の神経再生に伴う神経接着分子の発現:川野 仁,堀江正男(東京都神
経科学総合研究所解剖発生学部門,堀江秀典(横浜市立大学医学部第1生理)
7.シュワン細胞におけるGDNFおよびGDNFファミリー受容体の発現調節:渡部和彦(東
京都神経科学総合研究所神経病理学部門)
第10回(平成11年3月20日)
場所:慶應義塾大学医学部・新教育研究棟4階講堂
A.Mini
Symposium「代表的な培養細胞株の扱い方とその応用」
1.ES細胞:三五一憲(国立健康栄養研究所老人健康栄養部)
2.P19細胞:水野一也(東京都神経科学総合研究所微生物学・免疫学研究部門)
3.PC12細胞:大谷-金子律子(聖マリアンナ医科大学解剖学)
4.グリオーマ細胞株:佐和弘基(杏林大学医学部脳神経外科)
5.MTT-S(GH産生細胞株):野上晴雄(慶應義塾大学医学部解剖学)
6.遺伝子導入細胞株(CHO細胞ほか):武田泰生(東京都老人総合研究所細胞認識部門)
B.Exhibition:ナルジェ・ヌンク・インターナショナル(株)その2
C.Talk
1.酸化ストレスによるシグナル伝達増強と神経細胞死:竹腰 進(東海大学医学部病態診断
系病理学部門)
2.神経細胞生存におけるコレステロールの果たす役割:道川 誠(国立長寿医療研究センタ
ー痴呆疾患研究部)
3.転写因子(マスター遺伝子)に制御される標的分子(エフェクター分子)の神経内機能:
武内恒成(国立奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)
4.神経細胞への遺伝子導入:pseudotyped
lentivirus vector:望月秀樹(順天堂大学脳神
経内科)
5.COS1
cell
由来因子による末梢神経再生初期過程の調節:堀江秀典(横浜市立大学医学
部第1生理学)
第11回(平成11年9月11日)
場所:東京医科歯科大学・医科新棟5階症例検討室
A.Mini
Symposium「ニューロンの初代培養法とその応用」
1.中脳ドパミンニューロンの培養:竹島多賀夫(鳥取大学医学部脳神経内科)
2.海馬,中隔野ニューロンの培養:柏谷義宏(鳥取大学医学部脳神経内科)
3.運動ニューロンの培養:荒川義弘(東京大学医学部付属病院分院薬剤部)
4.小脳顆粒細胞の培養:永田 功,黒田純子(東京都神経科学総合研究所神経細胞生物学)
B.Exhibition:ナルジェ・ヌンク・インターナショナル(株)その3
C.Talk
1.Apoptosis
in vivo and in vitro study in neonatal weaver mouse; histogenesis of
cerebellar
dysplasia:石原好弘(東京都神経科学総合研究所神経病理)
2.Rat
C-CAM (CD66a, BGP homologue) expression in the developing brain:
佐和弘基(杏林大学医学部脳神経外科)
3.神経細胞への遺伝子導入:adeno-associated
virus vector:望月秀樹(順天堂大学脳神
経内科)
第12回(平成12年3月18日)
場所:順天堂大学医学部6号館2階
A.Mini
Symposium「GDNF:基礎と臨床」
1.特別講演:神経栄養因子による神経疾患治療の可能性:阿部康二(岡山大学医学部神経内
科)
2.神経芽腫cDNAプロジェクトによる新規エンドテリン変換酵素のクローニングとその生
理的意義:中川原 章(千葉県がんセンター生化学研究部)
3.パーキンソン病の遺伝子治療:村松慎一(自治医科大学神経内科)
4.運動ニューロン損傷の遺伝子治療:渡部和彦(東京都神経科学総合研究所神経病理)
B.Exhibition:ナルジェ・ヌンク・インターナショナル(株)
C.Talk
1.海馬苔状線維の発達を蛍光色素DiIとポリシアル酸(神経細胞接着分子の糖鎖)抗体を使
って見る−in
vivo
から海馬切片培養の研究へ−:石 龍徳(順天堂大学医学部第2解
剖)
2.神経栄養因子ミドカイン:神経芽細胞発生期のラット胎仔脳の病巣修復過程における変
化:菊池香会(東京都神経科学総合研究所神経病理)
3.新規RNAベクター(センダイウイルスベクター)による神経細胞への遺伝子導入の試み:
福村正之(ディナベック研究所)
第13回(平成12年9月30日)
場所:東京医科歯科大学・医科新棟5階・第2症例検討室)
A.Mini
Symposium「神経系構築のダイナミズム - 神経接着分子 L1
とその仲間たち - 」
1.多機能分子
L1
の最近の話題:武田泰生(東京都老人総合研究所細胞認識部門)
2.
Secret life of the cell adhesion molecule L1: Intracellular L1 trafficking and
axon
growth:上口裕之(理化学研究所脳科学総合研究センター発生・分化研究グループ
)
3.神経成長の制御機構
-細胞接着分子とカルシウムを巡って-
:竹居光太郎(科学技術振興
事業団・ERATO・御子柴細胞制御プロジェクト)
4.神経接着分子とミエリネーション:伊藤康一(東京都臨床医学総合研究所炎症研究部門)
B.Exhibition:ナルジェ・ヌンク・インターナショナル(株)(15分)
C.Talk
1.神経細胞の極性や細胞機能調節に関わる新規アクチン結合分子群:武内恒成(名古屋大学
大学院理学研究科生命理学専攻機能調節学講座)
2.酸化型ガレクチンー1のマクロファージを介した神経再生促進作用:堀江秀典(横浜市立
大学医学部第1生理)
3.N-[4-(3-ethoxy-2-hydropropoxy)
phenyl] acrylamide selectively induces apoptosis
of
cerebellar granule cells in vivo and in vitro in rats:田中剛太郎(大鵬薬品工業(株)
安全性研究所)
4.アルツハイマー病発症機構においてコレステロールの果たす役割の検討:道川 誠(国立
中部病院長寿医療研究センター痴呆疾患研究部)
5.アルツハイマー病及びパーキンソン病モデルでのD-β-ヒドロキシ酪酸による神経保護効
果:柏谷義宏(鳥取大学医学部脳神経内科)
第14回(2001年3月24日)
場所:順天堂大学医学部6号館2階
A.Mini Symposium「神経幹細胞の基礎から臨床への展開」
1.成体の海馬に存在する神経幹細胞−研究の歴史と最近の話題:石 龍徳(順天堂大学医学部第2解剖学)
2.p53欠損マウスからの神経幹細胞株の樹立と解析:友岡康弘(東京理科大学基礎工学部生物工学)
3.成体組織の神経幹細胞−その性質と再生能:中福雅人(東京大学大学院医学系研究科神経生物学)
4.Bone marrow to neuron? - GFP
transgenic mouse骨髄移植モデルによる検討:望月秀樹(順天堂大学医学部脳神経内科)
5.グリアの幹細胞:阿相皓晃
(東京都老人総合研究所神経生物学)
B.Exhibition:日本ミリポア(株)
C.Talk(各30分)
1.Visualization of dynamic
behavior of neuroepithelial cells in developing mouse brain:永井健治(理化学研究所細胞機能探索)
2.運動ニューロン,運動神経に発現するガングリオシド:吉野 英(国立医薬品食品衛生研究所)
3.疾患モデルマウスからの培養シュワン細胞株の樹立:渡部和彦(東京都神経科学総合研究所分子神経病理)